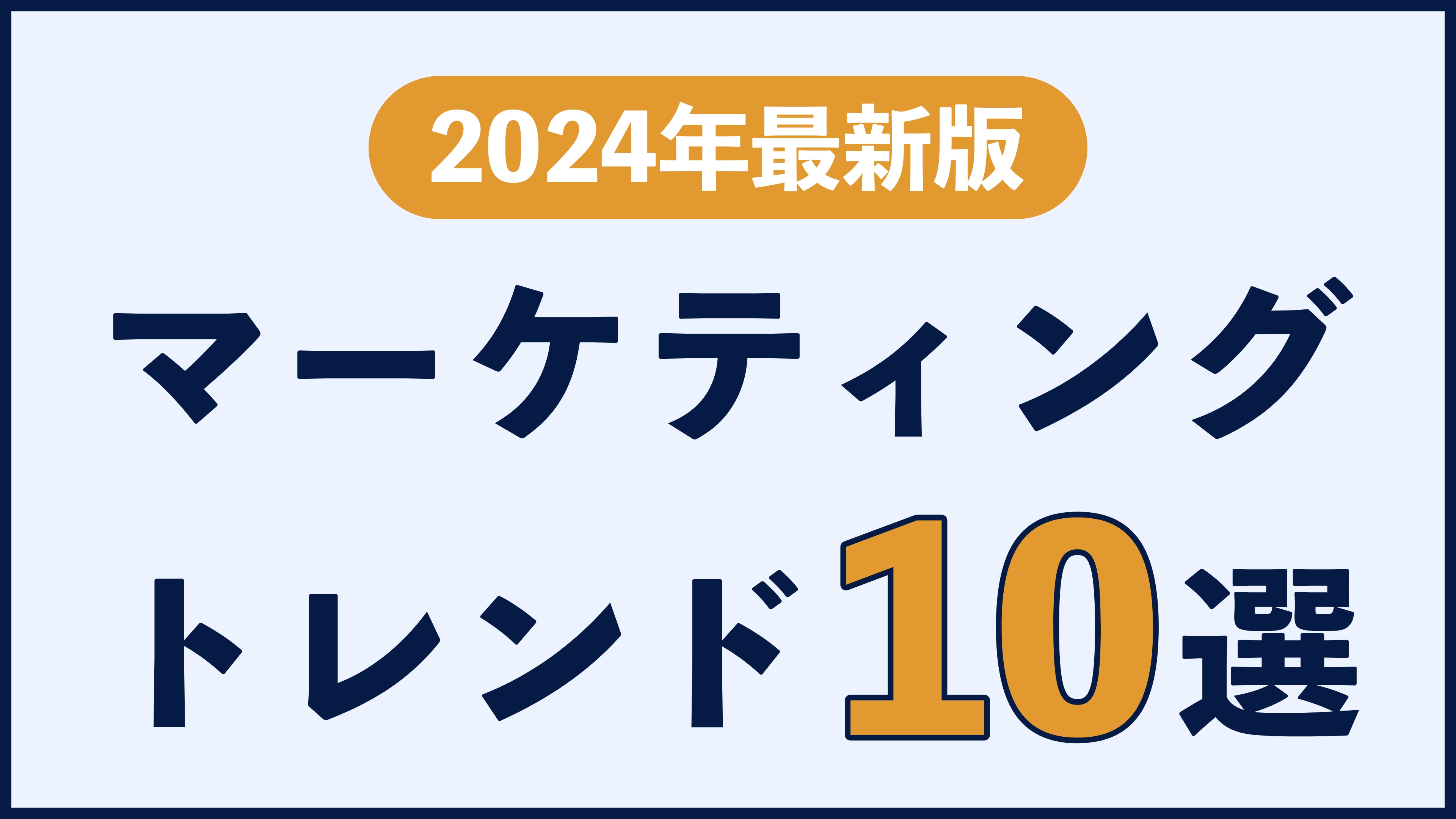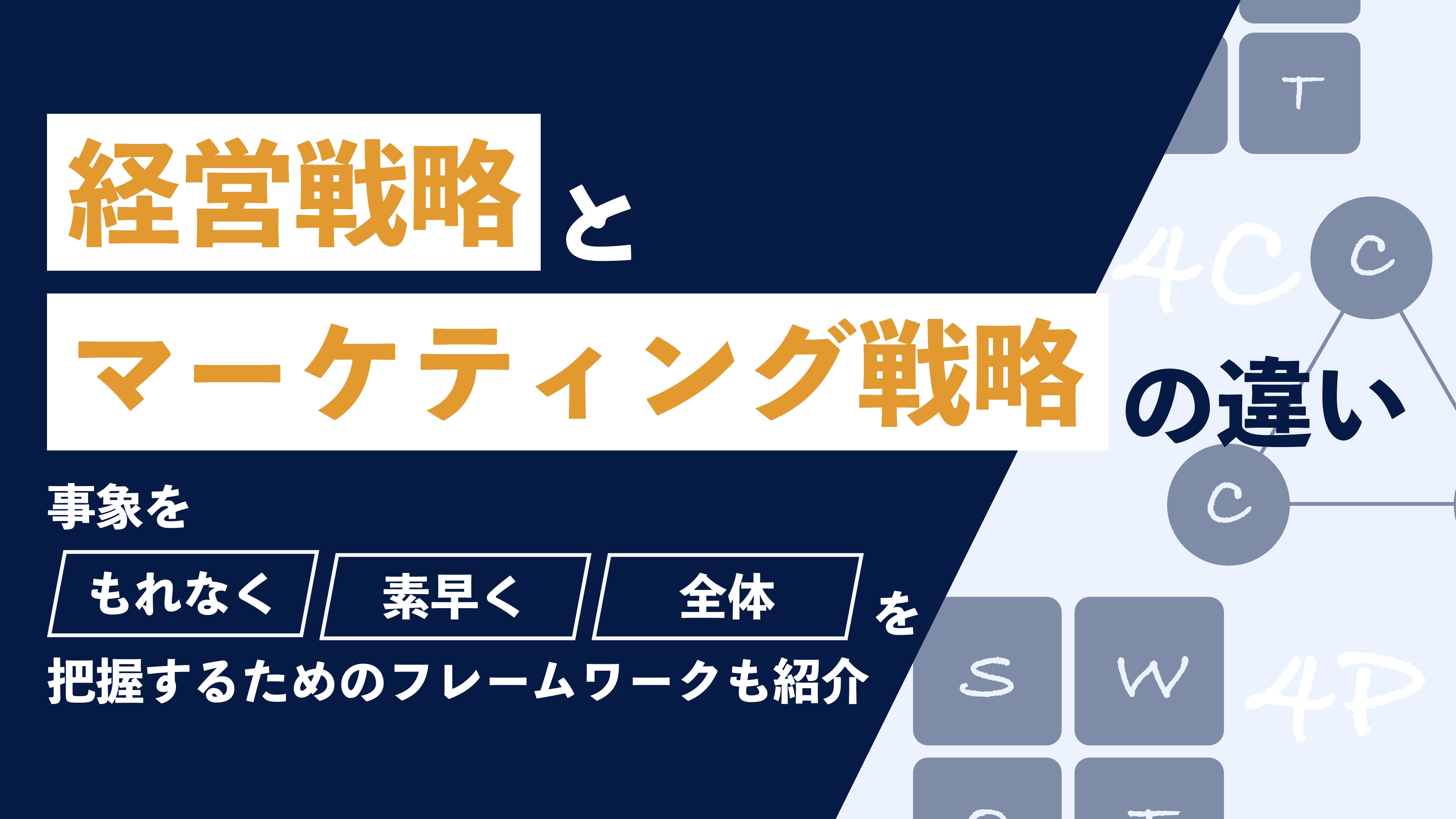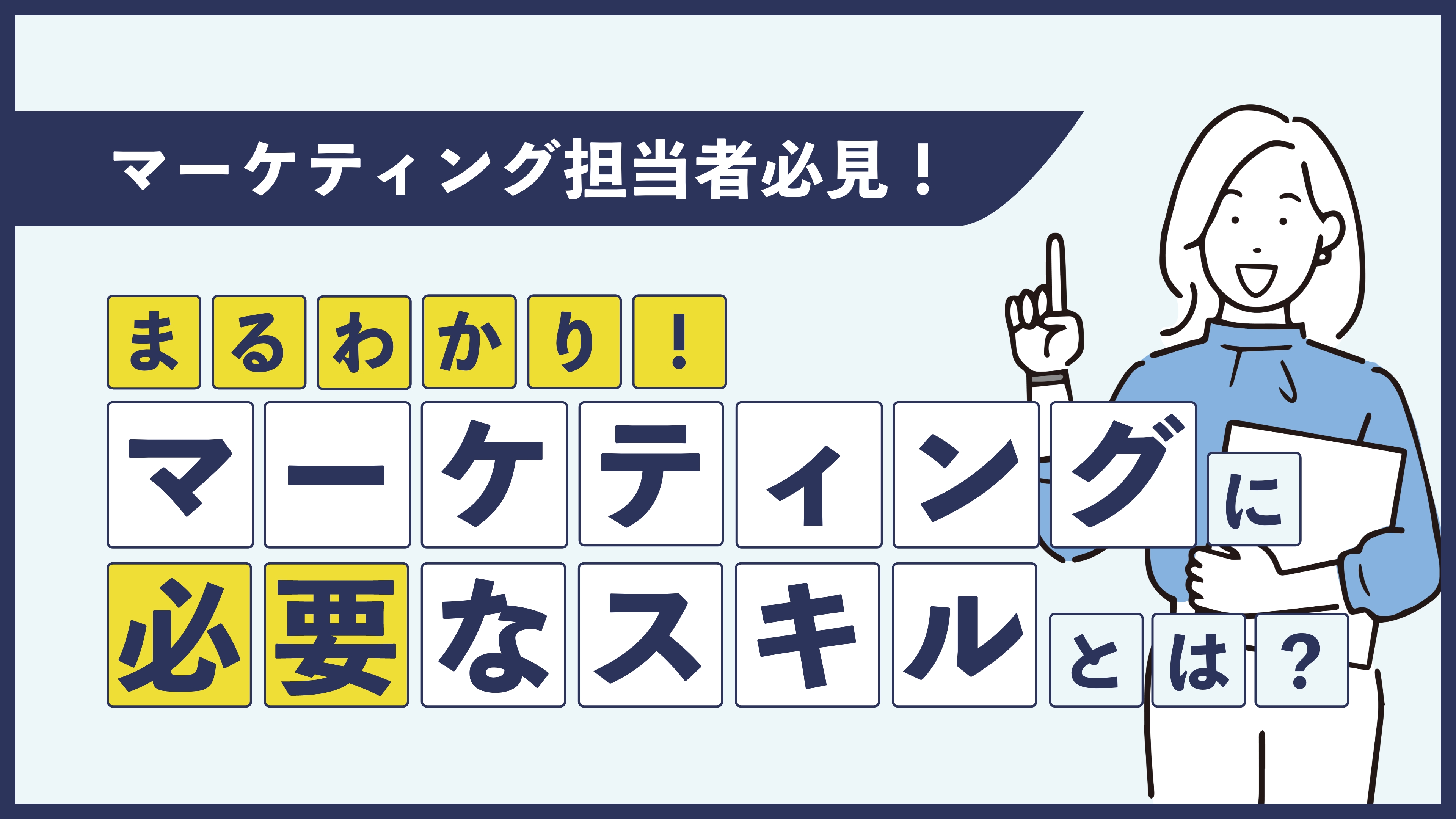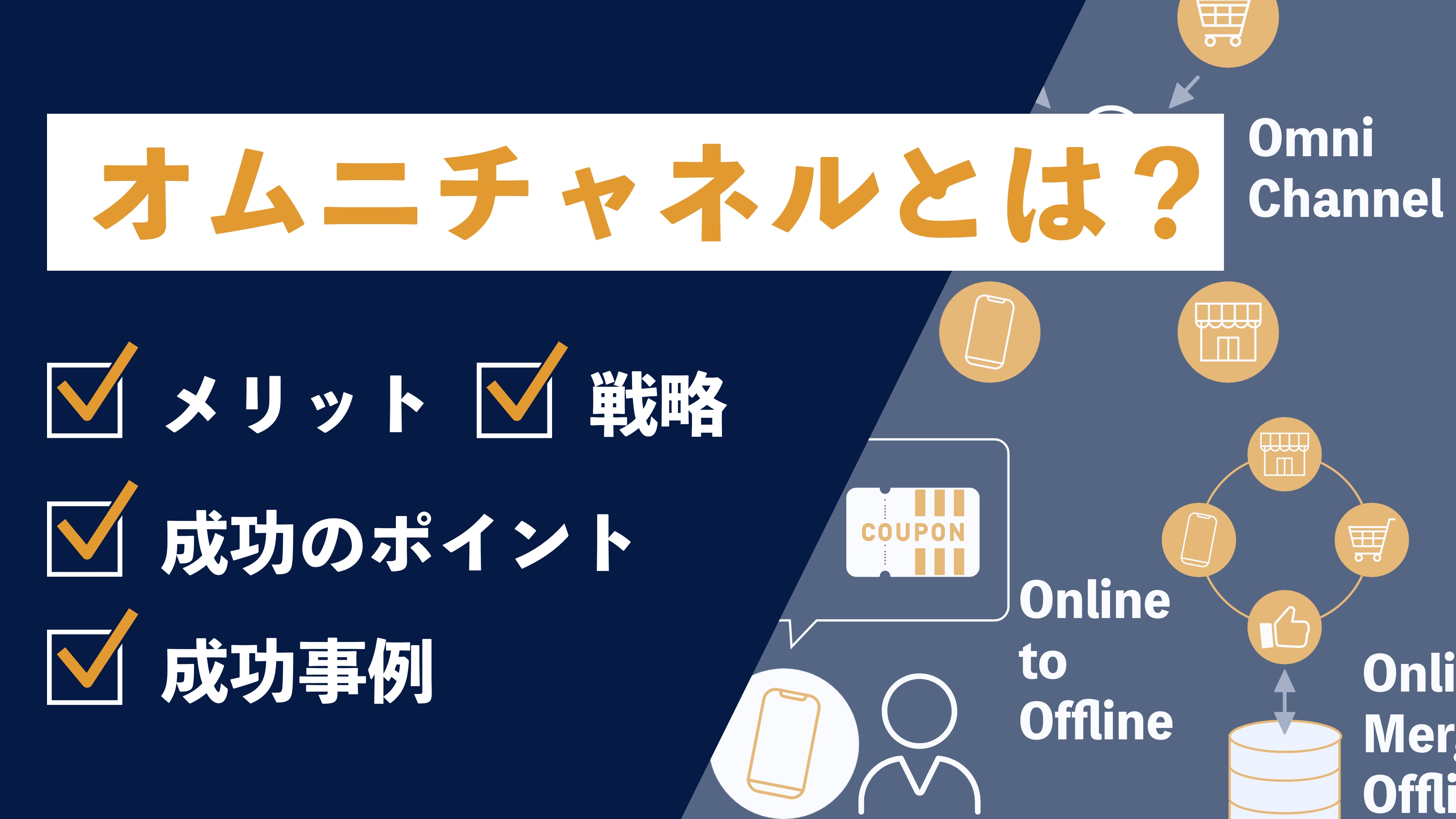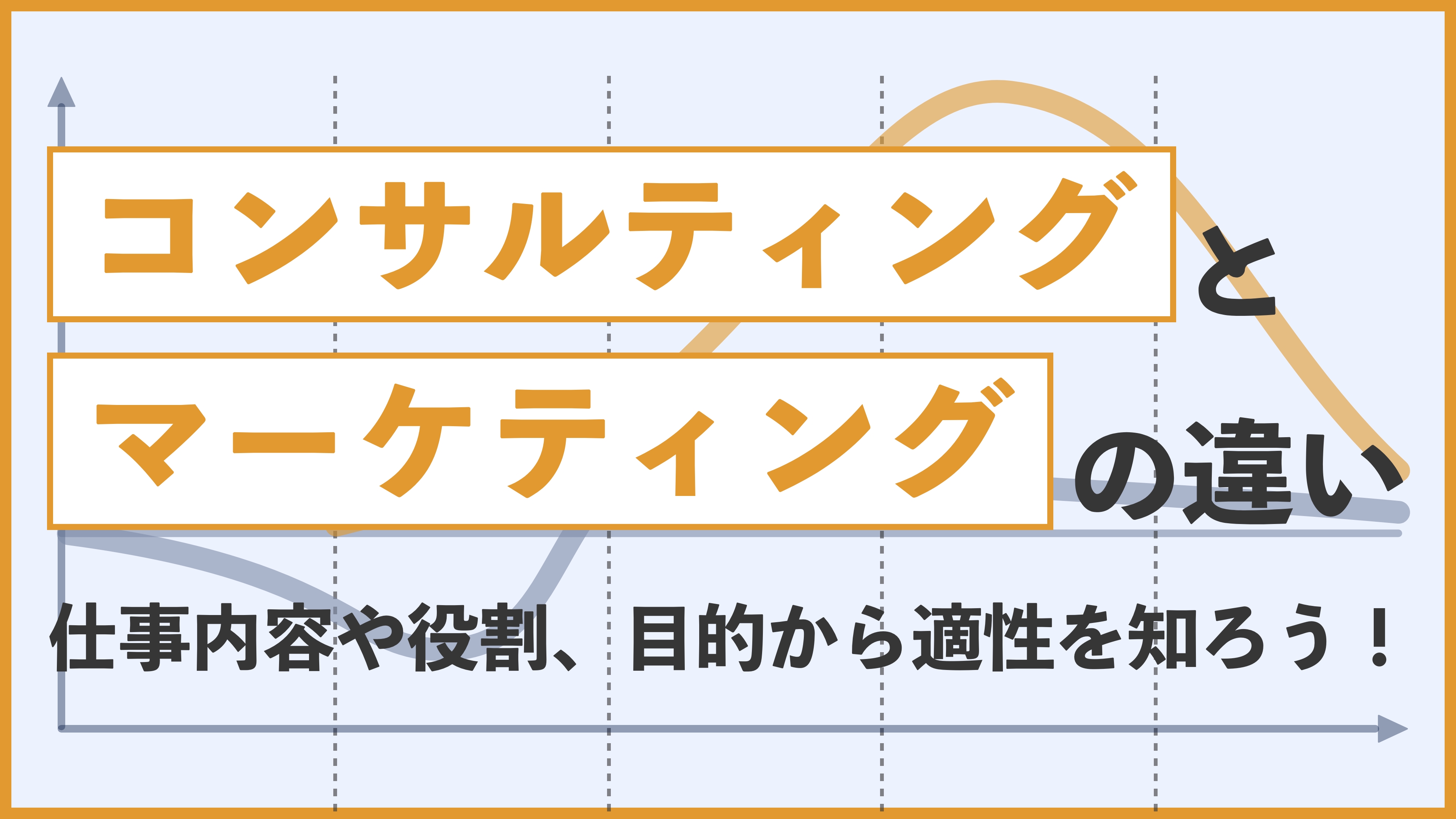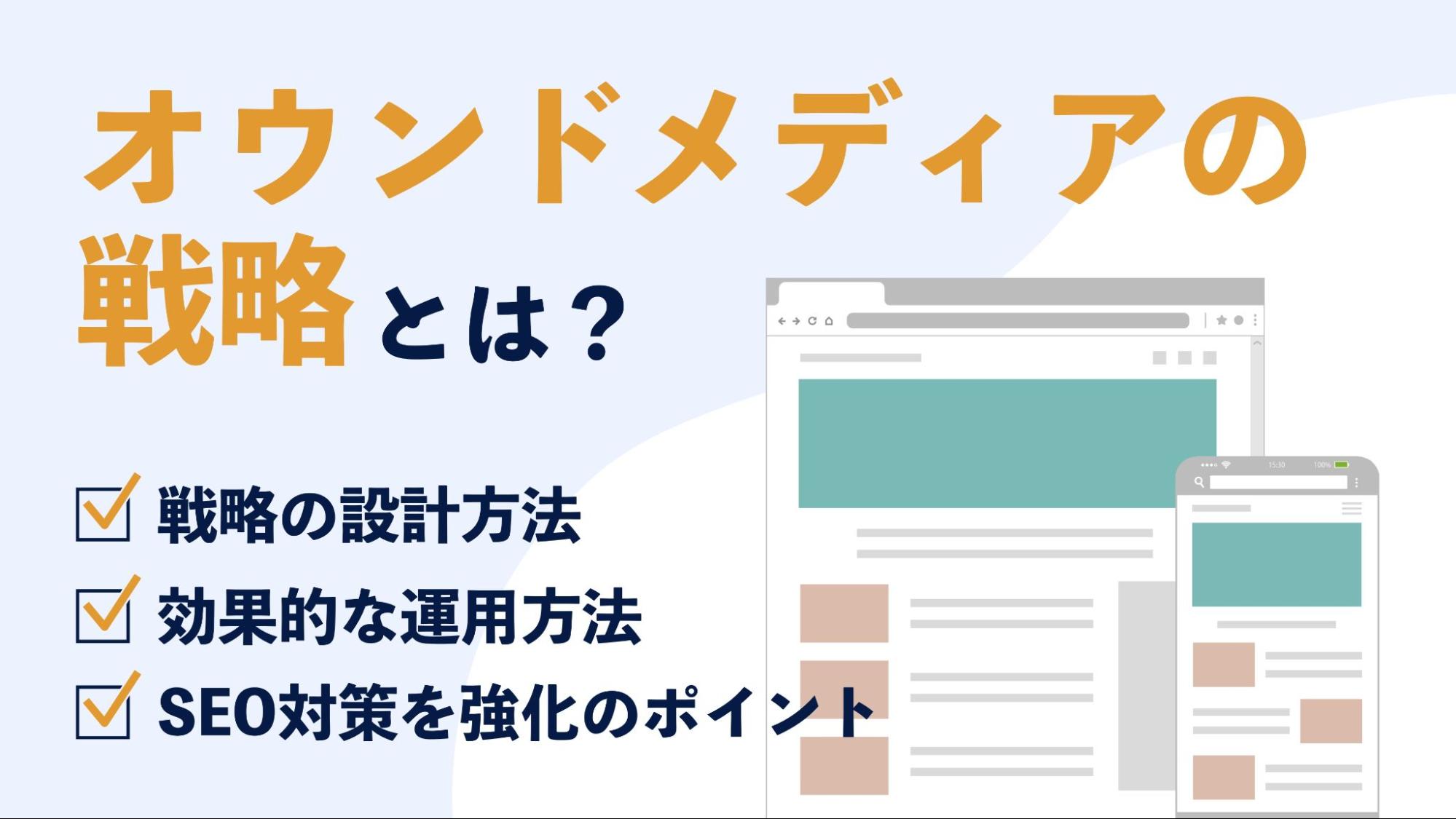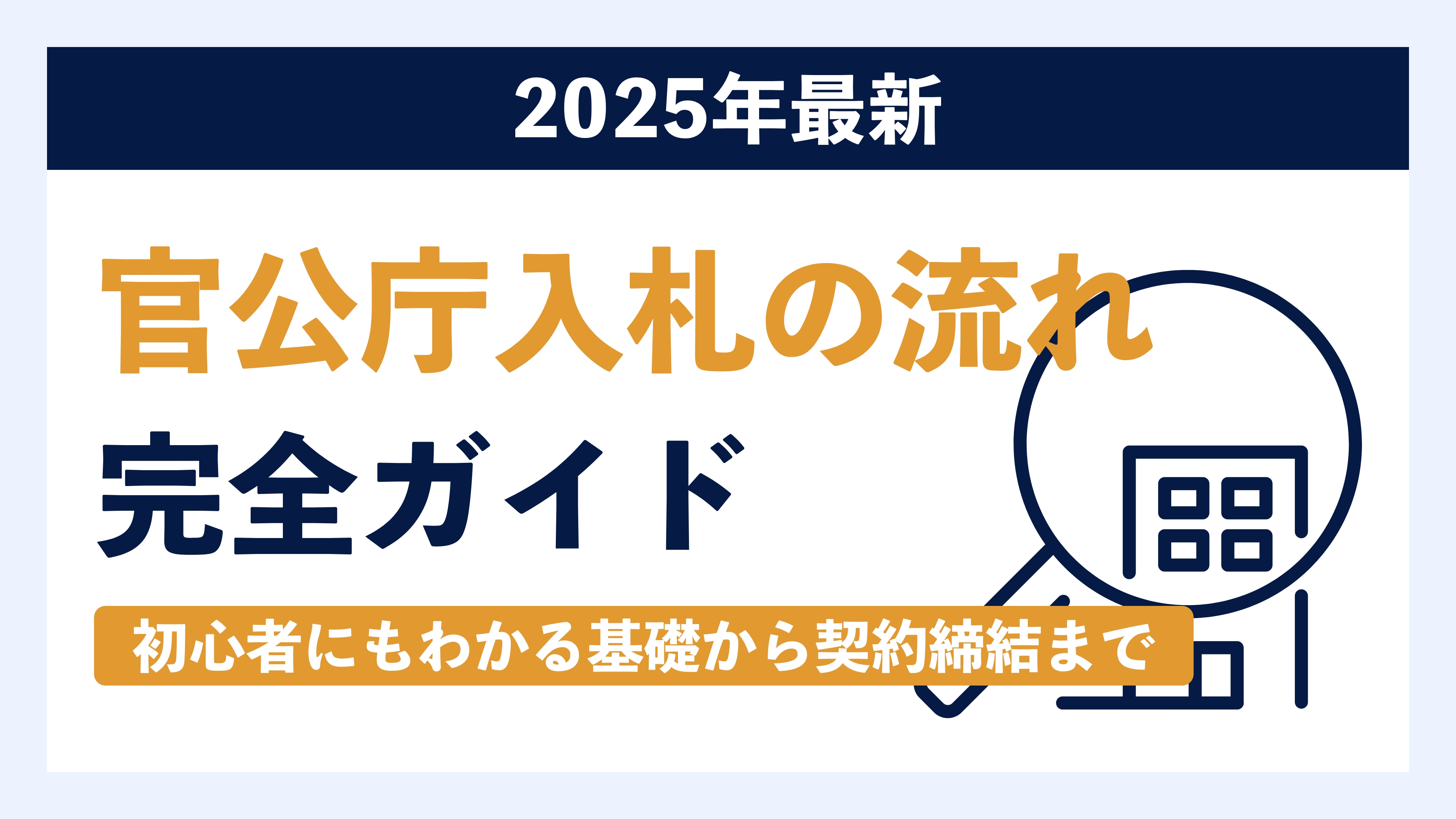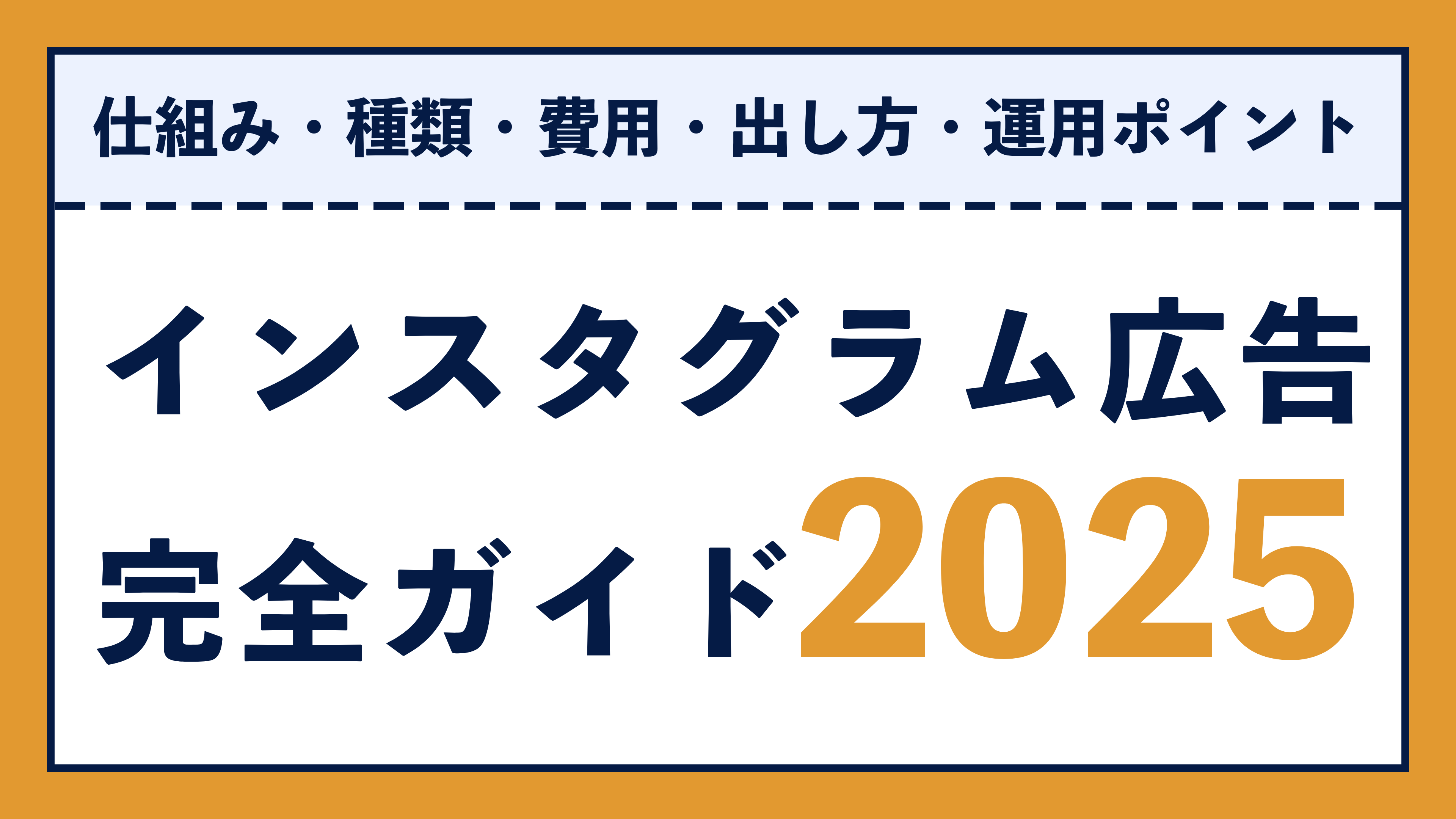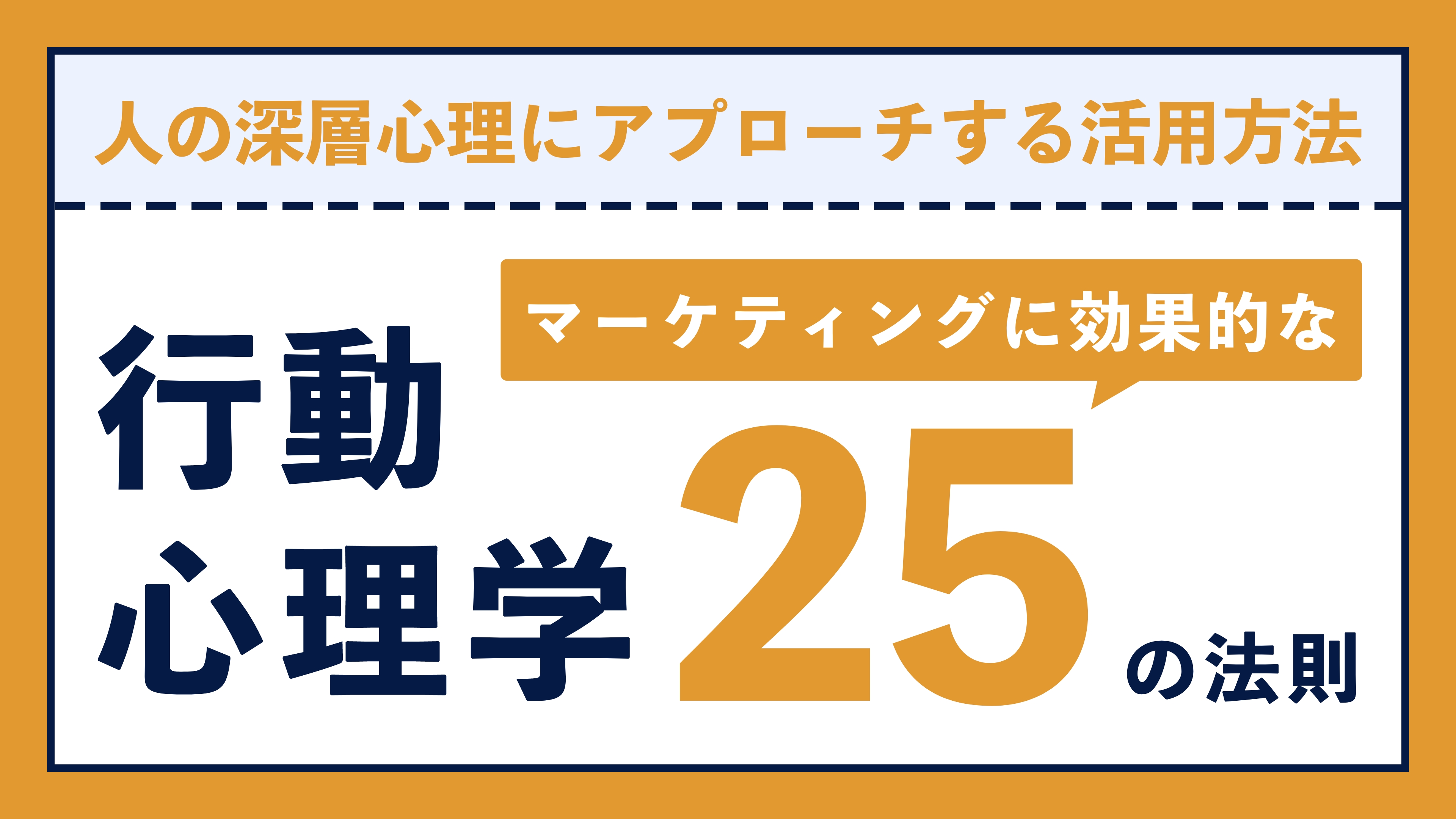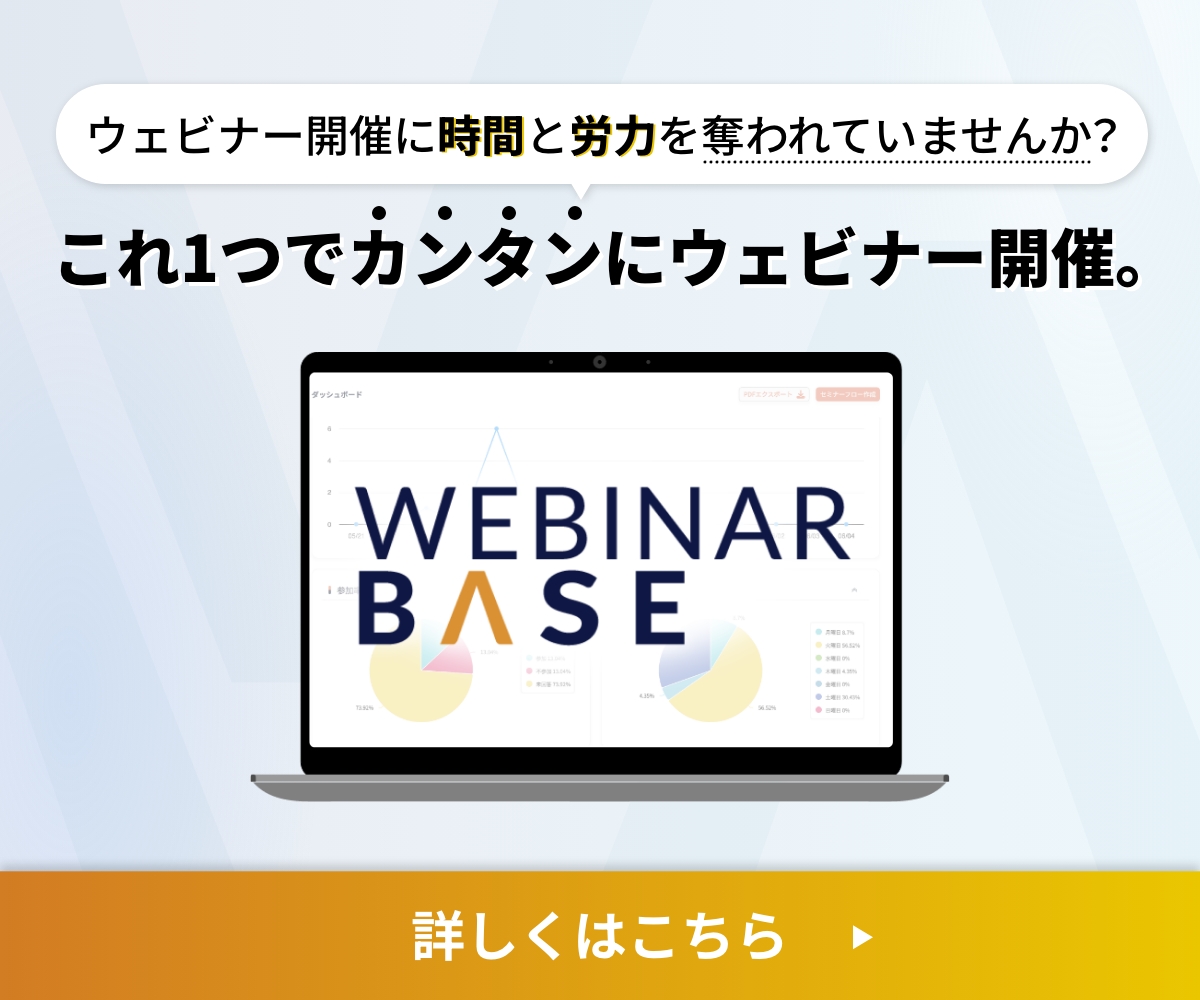新規事業の認知拡大方法で悩んでいませんか?ー展示会営業マーケティングがおすすめ理由とは?ー
マーケティング
.png)
はじめに
- 新規事業をもっと知ってもらいたい
- 認知拡大、知名度を上げたいが、どの方法が効果的なのかわからない
- 限られた予算での効果的なマーケティング手法が知りたい
このような悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。
ビジネスの成長には、多くの人々に新しい事業やサービスを知ってもらうことが不可欠です。
そんな時に強力な武器となるのが展示会営業マーケティングです。
短期間で多くの潜在顧客に直接アプローチできる展示会は、製品やサービスを実際に体験してもらう絶好の機会です。
この記事では、なぜ展示会営業マーケティングが新規事業の認知拡大におすすめなのか、その理由を詳しくご紹介します。
そもそも展示会営業マーケティングとは
展示会を利用して製品やサービスを直接的に紹介し、商談や販売活動を行う営業手法のことを指します。
企業がブースを設け、訪れる来場者と対話することで、直接的なコミュニケーションを通じて顧客を獲得し、ビジネスを促進することを目的とします。
認知拡大ために展示会をおすすめする理由
展示会営業のように、直接的な対話ができる営業活動である訪問営業では、対話人数が一般的に8人〜15人と言われていています。
しかし、展示会での営業活動では、対話人数が一般的に、1日で20〜40人と言われており、その差はなんと2.5倍です。
そして、
- 目立つブースデザイン
- ビジュアルコンテンツ(高品質の画像、ビデオ、パンフレット、カタログ)
- 統一されたブランドイメージ(ブランドの一貫性)
- 特典やプレゼント
などの視覚的な効果を活用して、効率的にブランドや製品の認知度を向上させる場として非常に有効的です。
展示会営業の効果
1.リードジェネレーション獲得
展示会では、名刺交換やコンタクト情報の収集を通じて、多くの見込み顧客(リード)を獲得できます。
これにより、後日フォローアップを行い、商談へと繋げることができる可能性が高いです。
2.市場調査と競合分析ができる
展示会に参加することで、業界の最新トレンドや競合他社の動向を把握することができ、自社の戦略を強化させることができる可能性があります。
3.ファン獲得
直接対話や実演などを通して、顧客との信頼関係を築くことは、ブランドのファン獲得に繋がります。
4.新製品・サービスのフィードバック収集
来場者から直接フィードバックを得ることで、製品やサービスの改善点を把握し、今後の開発に活かすことができます。
展示会の種類とそれぞれの目的
1.ビジネスショー(商談展、商談会、合同展示会)
- 主に業界関係者やビジネスパートナーを対象とした展示会
- BTOB形式で行われ、商談や契約の機会を提供
【目的】
- 新規取引先の開拓
- ビジネスネットワーキング
- 業界トレンドの把握
2.パブリックショー
- 一般消費者を対象とした展示会
- BTOC形式で行われ、幅広い参加者に対して製品やサービスを紹介
【目的】
- 製品やブランドの認知度向上
- 消費者からのフィードバック収集
- 即時販売やプロモーション
3.プライベートショー(主催展示会)
- 起業が自社で主催する展示会
- 特定の顧客やパートナーを招待し、製品やサービスを集中的に紹介
【目的】
- 顧客との関係強化
- 新製品やサービスの独自発表
- クローズドな環境でも商談
4.展示即売会(動員催事、セール)
- 製品やサービスの販売を目的とした展示会
- 即時販売を行い、売上を直接的に上げることを目指す
【目的】
- 売上の増加
- 在庫の処分
- 消費者との直接的な接触
5.オンライン展示会(バーチャル展示会)
- インターネットを通じて開催される展示会
- バーチャルブースやウェビナーを活用し、参加者とオンラインで交流
【目的】
- 地理的制約を超えた広範な参加者へのアプローチ
- コスト削減
- デジタルな参加型体験の提供
どのような人が来るのか(特徴と目的)
展示会には様々な目的や関心を持った人々が訪れます。
それぞれの来場者が異なるニーズや期待を持っているため、出展者はそれに対応するための準備を行うことが重要です。
1.業界関係者
- 特徴:既存の業界に従事しているプロフェッショナル
- 目的:最新の業界動向や技術情報を収集
2.バイヤー
- 特徴:企業の購買担当者や仕入れ担当者
- 目的:商品の品質や価格を確認し、購入の検討を行う
3.潜在顧客(リード)
- 特徴:まだ購入には至っていないが、興味や関心を持っている個人や企業
- 目的:製品やサービスの情報収集
4.メディア関係者
- 特徴:ジャーナリスト、ブロガー、インフルエンサーなど
- 目的:新製品やサービスの発表を報道
5.投資家
- 特徴:ベンチャーキャピタリストやエンジェル投資家など
- 目的:有望なスタートアップや革新的な企業を発見
展示会営業マーケティングとその他のマーケティング活動との違い
| 展示会営業マーケティング | デジタルマーケティング | 直販 | 広告 | |
|---|---|---|---|---|
| 直接対話 | ◯ | × | ◯ | × |
| 実物展示・デモ | ◯ | × | △ | × |
| リーチ | △ | ◯ | × | ◯ |
| コスト効率 | △ | ◯ | × | × |
| リアルタイムフィードバック | ◯ | △ | ◯ | × |
| ターゲティング精度 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
7.展示会営業マーケティングのメリット・デメリット
メリット
1.見込み顧客とその場でコミュニケーションが取れる
これは、展示会営業の最大のメリットともいえます。
なぜなら、展示会営業では、製品やサービスに対する顧客の反応をその場で観察することができ、顧客の興味や関心、疑問点をリアルタイムで把握することができるからです。
そして、「顧客の要望」などをその場でヒアリングすることで、迅速な問題解決や顧客の満足度向上につながります。
また、対面でのコミュニケーションは、信頼関係構築にも繋がり、次への接点にもなります。
そのため、展示会営業マーケティングは、ビジネスチャンスの貴重な場でもあります。
2.短期間での多くのリード獲得ができる
展示会は、大規模なら、数万から数十万人、中規模なら数千から数万人もの人が来場すると言われています。
また、展示会には特定の業界や市場に関心のある多くの参加者を引きつけるため、短期間で多くの潜在顧客にアプローチすることができます。
3既存顧客との信頼関係向上
展示会には、既存顧客も訪れる可能性があります。
自社の商品のさらなる魅力や、新商品の宣伝ができる機会にもなり、長期的な関係構築にも繋がるでしょう。
4ブランド認知の拡大
大規模な展示会では、メディアや業界関係者(業界のリーダーやインフルエンサーなど)も取材に訪れることが多く、さらに認知を広めることができます。
また、顧客に実際に製品やサービスを体験してもらうコーナーを作ることや、ブースデザインや装飾にこだわることで、顧客の印象に残り、自社のアピールにも繋がります。
5.競合他社のリサーチをすることができる
展示会では、多くの競合他社も出展しています。
競合他社がどのようなブースを出しているのか、どのような訴求をしているのかを知ることで、自社の課題や改善点が見つかるかも知れません。
参考にし、自社の戦略を強化させることができるという面でも、とても良い機会だといえます。
デメリット
1.準備や運営に時間と労力がかかる
展示会は、明確な目標設定、ブースデザイン、プロモーション素材の準備、物流と設営、スタッフの訓練、そして展示会後のフォローアップまで行わないといけないため、かなりの労力がかかります。
そのため、開催が近づくにあたって、社員の通常業務に影響が出るケースもあるため、これらのことは頭において、検討することが良いでしょう。
2.正確な効果測定を数値化することが難しい
展示会でどれだけのリード(見込み顧客)を獲得したかは比較的わかりやすいのですが、展示会参加によってブランドの認知が拡大したかどうかは、数値化することが難しいです。
それに伴い、展示会参加にかかる全てのコスト(ブース費用、スタッフ費用、プロモーション費用など)に対して、展示会によってどれだけの利益がもたらされたかというROI(投資対効果)の算出も極めて困難です。
獲得した全てのリード数が、正確なリードにはならないということを頭に入れておく必要があります。
3.フォローアップの必要性
展示会ては、多くの名刺や新規のリード顧客が増えることが予想されます。
そのため、その名刺や顧客のデータを管理し、適切なタイミングで顧客への連絡、メールなどのフォローアップを行わなければならなりません。
非常に多くの時間と手間がかかってしまうことを頭に入れておく必要があります。
これらのフォローアップを怠れば、せっかくの展示会での成果が無駄になる可能性もあります。
フォローアップを効率化し、展示会の効果を最大化する必要があります。
まとめ
展示会営業が認知拡大に効果的な理由を解説してきました。
現在、新規事業の認知拡大のために悩まれている方には、ぜひ検討していただきたい手法です。
とはいえ、「成果の不確実性」に不安を抱かれる方もいると思います。
そこで、独自の手法により出展コストの33倍売るノウハウを伝える日本唯一の専門家が「売上増につながる展示会営業の勝ちパターン」を紹介したセミナーがございます。
展示会での効果を最大化させるためにも、ぜひご参加ください!
↓お申し込みはこちらから↓
https://seminarbase.com/detail/64

.jpg)